このページの取り組みが、7月18日に発売のCQ ham radio誌に記事として掲載されました。 タイトルは大胆不敵にも「CW触覚モールス通信のススメ」。 ・・・・もし「体験したい」という奇特な方がいらしたら、ハムフェア会場に持っていきますのでお声がけください。
掲載にあたっては、日本点字図書館、全国盲ろう者協会、東京盲ろう者友の会はじめ、多くのご関係の方々からアドバイスをいただきました。 またCQhamradio編集部のJE1HYR井端さんには、とりとめのない、でも「盲ろう」といういままであまり同誌では前例のないテーマである拙文を、的確かつわかりやすく記事化することにご尽力いただきました。 まずこちらの皆様に、こんなHPの片隅からではありますが、厚く御礼申し上げます。

内容はこのHPのどこかに書いたものばかり・・・・というわけでもありません。 けっこうな部分で前記諸団体の資料を引用させていただき、記事にも目通しをしていただきました。 モールスは振動に変換するだけで、視聴覚をつかわずに触覚で扱えるメディアになるはずです。
ヒューマンスケールのデジタル通信として、視覚障がい者が使っている「点字」とは兄弟分、どちらも200歳ぐらい。 いまや私たちアマチュアだけが使っている「モールス符号」は、そのまま電波にも乗せられるし、活字にもなるし、ケータイの振動にもなるし、テープライターに打ってその辺に貼っておいてもOK、という変幻自在な言語といえます。
今回、電信愛好家の方々に「そういった見方もできるのでは?」と言いたいがために記事を書いたといってもいいでしょう。 とはいえ、私はごく初歩的とされているトランジスタの回路設計もろくにできないので、当初「回路図は小さく載せるだけ」ということで安心していたのですが、予想に反してかなりデカデカと掲載されてしまいました。
![]()
ちょうど前号(7月号)の同誌は、「モールス通信の魅力」というテーマで特集が組まれ、Dit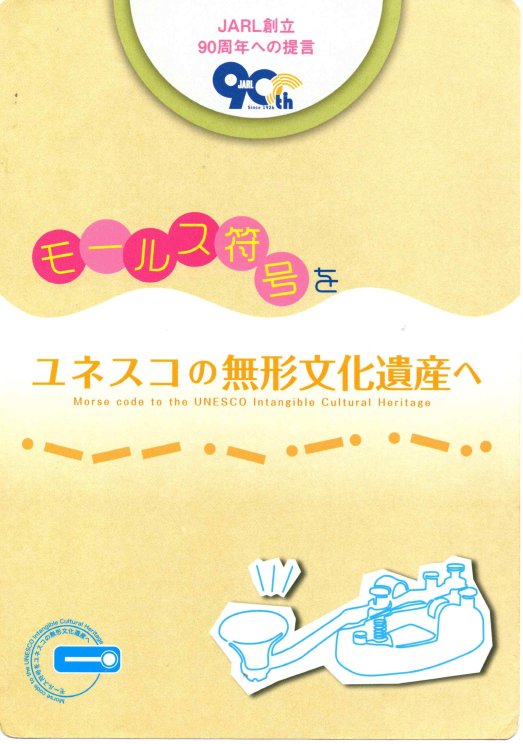 -Dah-Chatの作者であるJI1JDI神宮さんをはじめとする諸OMの興味深い、読みごたえのある記事が満載でした。 拙稿は「モールス通信の魅力」を語るものではないかも知れませんが、電気通信の黎明期にできたものの持っている「無碍融通さ」を、振動に変えてみるという切り口を通してお伝えできればと思っています。
-Dah-Chatの作者であるJI1JDI神宮さんをはじめとする諸OMの興味深い、読みごたえのある記事が満載でした。 拙稿は「モールス通信の魅力」を語るものではないかも知れませんが、電気通信の黎明期にできたものの持っている「無碍融通さ」を、振動に変えてみるという切り口を通してお伝えできればと思っています。
こんな不思議なものが、電気通信の世界でいまだに私たちアマチュアだけが嬉々として第1選択として愛用している・・・そのことだけとっても、世界遺産に値すると思うのは私だけでしょうか?
今回、同誌には初投稿にもかかわらず、望外の8ページもの紙面をいただきました。 それでも初稿では、振動受信の正読率、JA1AB故市川OMの取り組み、アマチュア無線機のUD対応の話、電波文化祭でのハートウエアラボの米山さんとのコラボ話など、もっと多くの話を詰め込んでいました。 考えてみれば、このHPにも書いていないこともありましたので、機会をみてどこかにまとめておこうと思います。